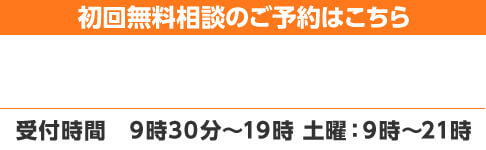目次
少年事件とは
刑法は、14歳以上の者に対する処罰を規定しています(「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」(刑法41条))。
そして、少年法は、20歳未満の者に対して、刑法に加えて特別な規定を置いています。少年法では、20歳未満の者を少年と呼称しているため、少年が犯した事件については、少年事件や少年犯罪といわれています。少年に対しては、刑罰よりも保護(少年の健全な育成を目指す処分)を行うことが少年法の目的(少年法1条)であるため、成人の刑事裁判とは違ったプロセスで行われます。
※令和5年4月1日、改正少年法の施行~「特定少年」という概念の導入
民法で成人年齢が18歳に引き下げられました。これまで少年法は、20歳未満を「少年」として取り扱ってきましたが、18歳、19歳の少年を「特定少年」とする運用に改正されました。そして、少年法は特定少年に対し、逆送の拡大、実名報道の解禁など17歳以下の少年とは異なる措置を講じるとしています。
少年事件の例外
年齢切迫事件
少年の年齢が20歳まであと数ヶ月で、審判の時点で成人となってしまう可能性のある場合には、「年齢切迫」事件となり成人事件として扱われることもあります。
逆送事件
少年が死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について刑事処分が相当だと認めた場合、事件を検察官へ送致し、成人の刑事事件と同じプロセスで手続きが進行します。
身体拘束が予想される期間
⇒勾留が却下されると2、3日
⇒勾留、勾留に代わる観護措置が決定するとさらに10日(例外的)
⇒家庭裁判所に送致され観護措置が決定すると
最終処分を決定する審判までさらに2週間~4週間
⇒審判で少年院送致の決定が出た場合には決定に応じて身体拘束が継続
もちろん事件の内容によっては数日で釈放となる場合もありますが、最長の場合には捜査段階で23日間、家庭裁判所送致から審判までさらに4週間身体拘束を受けることになります。観護措置が決定してしまうと、長期に渡る身体拘束を受けることとなり、お子様の学校や会社への影響は避けられません。
少年事件の流れ
逮捕された場合の流れは、以下のようになります。
本記事では逮捕から観護措置までの流れを紹介します。少年審判についてはこちら。
①警察による捜査、検察への身柄送致
②検察の勾留、勾留に代わる観護措置決定(例外的)
③家庭裁判所送致・観護措置の審判
④審判
①逮捕から身柄送致
逮捕や勾留の手続きは、少年事件と一般の刑事事件で概ね違いはありません。
少年が逮捕された場合は最大で72時間、警察署の留置施設などで身体を拘束されます。逮捕された後は、事件の記録が警察から検察官に送られます。
②勾留と勾留に代わる観護措置
勾留期間は検察官が少年の勾留を延長、継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。裁判官が、勾留の決定した場合は最大で10日間身体拘束が継続されます。検察官が裁判官に勾留延長の請求をし、裁判官が勾留の延長を決定すると、さらに最大で10日間は身体拘束が継続されます。
もっとも、少年事件の場合「やむを得ない場合」でなければ勾留をすることができないと定められています(少年法48条1項、同法43条3項)。すなわち、少年法上においては、勾留は例外的な取扱いであり、場合によっては、勾留に代わる観護措置(勾留中に少年鑑別所等に身柄を送致してもらうこと)をお願いすることもできます。この場合は、少年鑑別所は、少年の健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うので、警察の留置所で勾留されているよりも良い環境で時を過ごせます(裁判所の運用上、勾留に代わる観護措置が認められることは多くはありません。なお、勾留に代わる観護措置には延長がありません。)。
弁護の方針
長期間にわたって身柄を拘束されると、少年の学業(停学、退学)等に支障が出ますので、いかに逃亡のおそれがないか、長期拘束されると如何に少年の健全な育成に支障が出るか等につき証拠をもって裁判所に示して、勾留されないようにすることが、早期の身柄解放には肝要となります。
また、共犯事件(複数犯)の場合、接見禁止処分(弁護士以外の者は面会を禁ずること)を付されることがありますが、少年事件の場合、通常、両親とは面会できる場合が多いです。もっとも、まれに両親との面会にも接見禁止処分が及ぶ場合がありますので、その場合の付添人活動としては、接見禁止の一部解除(両親には面会できるようにする手続)を申し立てることが考えられます。
③家庭裁判所送致・観護措置の審判
20歳以上の成人の刑事事件においては、警察から検察官へ事件が送致され、検察官が最終的に起訴不起訴を判断します。不起訴処分となった場合は、事件はそれで終了します。
しかし、少年事件の場合には、検察官が直ちに起訴不起訴の判断をするのではなく、すべて家庭裁判所へ送られます。これを、全件送致主義といいます。これは、少年に対しては、刑罰よりも保護(少年の健全な育成を目指す処分)を行うことが少年法の目的(少年法1条)であるからです。
〇観護措置
家庭裁判所の送致された日に、観護措置がとられるかどうかが判断されます。鑑別所での収容期間は2週間ですが、多くの場合は継続の必要があると判断され、4週間の収容となります。また、事件が、死刑や懲役刑にあたる重大事件であればさらに2回更新される場合があり、その際は最大で8週間収容されます。仮に、観護措置をとらない判断がなされた場合は、その日に身柄が解放されます。
なお、「鑑別」とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すことです。
弁護の方針
観護措置が決定されると少年は長期間鑑別所にいることになりますので、社会生活上、更なる支障が出る可能性が高いです。そこで、家庭裁判所送致当日に、裁判所は、観護措置をするか否かを決定するための審問を行うので、付添人(家庭裁判所に送致された後は、「弁護人」から「付添人」という名称に変わります。)としては、事前に裁判所に対し意見書を提出し、裁判官と面談して観護措置をとらないような働きかけをすることが考えられます。
事件が家庭裁判所に送られてから少年審判(成人事件における刑事裁判に当たります。)までは、より良い処分をもらう、または審判を開かないよう求める弁護活動を進めていきます。鑑別所では、鑑別技官により今までの生い立ちや非行事実を行ったときの心理状態等を事細かに聞かれます。鑑別技官による意見(鑑別結果通知書)がその後の処分の大きな影響を与えますので、どのような回答をするか、しっかり準備をする必要があります。その間、家庭裁判所の調査官による面談も行われます(観護措置が取られなかった場合でも、調査官による調査が行われます。)。家庭裁判所の調査官が作成する調査票は審判の重要な判断材料となります。
仮に、審判が開始されなかった場合(不開始)は、事件自体が終了します。