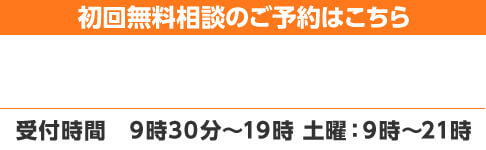目次
保釈・釈放について(違い)
釈放とは、被疑者や被告人が身体拘束から解放されることをいいます。(犯罪の嫌疑を受け、捜査の対象となっている人のことを、起訴前ならば被疑者、起訴後ならば被告人といいます。)
保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を現実の身柄拘束状態から解放する制度です。保釈も釈放の一種ではありますが、起訴後のみに請求できる点や保釈保証金の納付が必要になる点などに特徴があります。
保釈保証金の額は個々の事案に即して決定されるものですが、一応の目安として、「最低150万円、通常200万円」などと言われることがあります。一般的に、保釈保証金は高額であるため、すぐに用意することが難しいという場合もあるかもしれません。ですが、日本保釈支援協会による保釈保証金立替制度や全国弁護士協働組合連合会による保釈保証書発行制度等、保釈保証金を準備できない場合にも、保釈を請求することができるよう支援してくれる制度がありますので、こうした制度を利用することも選択肢の1つです。
保釈は、一時的に勾留の執行が停止されているだけですので、正当な理由なく刑事裁判を欠席したり、保釈決定の際に定められた条件に違反したりして保釈が取り消された場合には、再度身体が拘束されることになります。また、保釈が認められていたけれども、判決期日で実刑判決(一部執行猶予判決も含みます。)が言い渡されてしまったという場合には、保釈の効力は失効してしまうので、被告人は判決言渡し直後に法廷から連れ去られて、そのまま収容されてしまいます。この場合、すぐに再保釈の請求をすることが考えられますが、再度保釈保証金を納付する必要があるので、注意が必要です。ちなみに、再保釈における保釈保証金は、第一審における保釈保証金の金額に10%から50%上乗せした金額となることが多いようです。
保釈の趣旨
刑事事件には無罪推定の原則というものがあります。刑罰は有罪判決が確定して初めて行われるものであって、それ以前に刑罰を課すことはできません。
保釈は、保釈保証金の没収という心理的強制によって被告人の公判への出頭を確保し、罪証隠滅を防止することで、できる限り無用な身柄拘束を回避しようという趣旨の制度です。
逮捕や勾留は、被疑者・被告人に多大な肉体的・精神的苦痛を与えるものでありますが、刑罰ではありません。
刑事手続のために必要とはいえ、逮捕や勾留をされてしまえば行動の自由を奪われますので、帰宅することも仕事に行くこともできなくなります。被疑者や被告人とって、この制約の影響は非常に大きいです。
逮捕や勾留をされたために職場を辞めざるを得なくなったという事例は珍しくありません。
こうした事態を避けるためにも、起訴後は、積極的に保釈を求めていくべきでしょう。
保釈の要件
保釈は起訴された被告人に対して認められる制度ですが、どのような場合でも認められるというわけではありません。
保釈が認められる場合として、刑事訴訟法では、大きく分けて、権利保釈と裁量保釈という類型にわけられています。
権利保釈については、原則として認められると定められており、認められない場合が列挙されています。権利保釈が認められない場合に、裁量保釈を検討することになります。
裁量保釈においては、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情が考慮されます。
裁判所が保釈を認めた場合、保釈保証金の額も決められます。この保釈保証金は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされています。冒頭で、保釈保証金の額の一応の目安として、最低150万円、通常200万円というお話をしましたが、会社経営者や医師等、資力があると認められる被告人の場合には、500万円を超えるような保釈保証金が定められることもあります。
保釈後、被告人が裁判に出頭しない場合などは、保釈保証金が没取されることがあります。
保釈を求めようとするときには、保釈が認められるように裁判所を説得し、さらに、保釈保証金についても、被告人や被告人の家族が用意できる金額にするよう裁判所と調整をすることになります。
権利保釈
権利保釈は、当然の権利として認められています。しかし、次の場合には認められていません。
・被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
・被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人の氏名又は住居が分からないとき。
裁量保釈
権利保釈で述べた条件のいずれかに該当する場合においても、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して、裁判所が保釈を認める場合をいいます。
義務的保釈
捜査上の取り調べ期間中の勾留が不当に長くなった場合に、裁判所が保釈を認めることをいいます。
しかし、実際に適用される例はほとんどありません。裁判所において保釈が相当であると考える場合には、事実上、弁護人に対して保釈の申請をほのめかすような場合がまれにあります。
保釈申請は何度でもできますが、弁護人としては、裁判所が保釈を認めそうかどうか、裁判所を説得する事情を用意しつつタイミングを図ることもあります。
保釈後について
いずれの場合の保釈においても、裁判所からの出頭命令には必ず応じることが条件とされ、保釈中にそれに反して逃亡したり、証拠隠滅を図ったりした場合には保釈は取り消されたうえで保釈保証金の一部または全額は没収されることになります。
違反することなく裁判手続きが終了すれば、裁判の結果にかかわらず、保釈保証金は返還されます。保釈保証金を納付したら、どんな場合でも絶対に戻ってこないと思っていらっしゃる方もおられますが、違反なく刑事裁判を終えられた場合には納めた保釈保証金全額が戻ってきますので、ご安心ください。
保釈のタイミング・弁護士のできること
起訴される前
起訴される前に保釈の請求をすることはできません。ですが、釈放のための活動をすることはもちろんできます。
逮捕されたご本人(被疑者)は最短3日(72時間)で釈放され、日常生活に戻ることができる可能性があります。これは、刑事訴訟法に逮捕にともなう身柄拘束期間は72時間を超えてはならないと定められているからです。
しかし,身柄拘束期間中に,検察官が勾留を請求し,その後行われる裁判官における勾留質問の結果,裁判官が「勾留」の必要が認められると判断した場合には、その72時間に続きさらに10日間の身体拘束が生じてしまいます。また勾留はやむをえない場合に限り延長が認められており、延長期間を含めると勾留は最長20日間にも及ぶことがあります。つまり、逮捕されてしまうと、逮捕直後から検察官が起訴・不起訴の判断をするまで,最大で23日間は身体拘束の可能性があるということです。
弁護士は、なるべく勾留期間を短くする活動をすることでご本人やご家族をサポートさせていただきます。具体的には、①勾留決定阻止、②不起訴処分・処分保留,③略式請求の促し、④その他を目指します。
勾留決定阻止
長期間の身柄拘束はその後の社会生活に深刻な影響を与えることもあるため、できるだけ早く釈放させたいと誰もが思うでしょう。検察官による裁判官への勾留請求を阻止すること又は仮に検察官が勾留請求をしても裁判官において勾留をしない(勾留請求を却下する)旨の決定を得ることができれば、釈放してもらうことが可能になります。釈放されれば、事件は在宅事件に切り替わり、自宅から警察署に出頭して取調べを受けることになります。出頭での取調べは任意であるため、釈放後は自由に職場や学校に通うことができ、今までどおりの日常生活を継続することができます。
ただ,出頭は任意ですが,出頭を拒否しているとみられる場合は,再逮捕されるおそれもありますので,警察等の取調べには,出頭日時を調整してもらい,できるだけ応じた方がよい場合が多いと思われます。
勾留されるかどうかは逮捕されてから72時間以内に判断されるため、勾留阻止に向けた活動は急ピッチで進める必要があります。しかし、逮捕から3日間程度はご家族とご本人の面会は認められないことが多いため、弁護士が双方の橋渡しをすることでその後の迅速な対応を可能にします。
また、当事務所では,捜査に対する独自の経験や法律家としての知識、ノウハウを生かし、勾留の必要がないことを検察官或いは裁判官に面接して,罪証を隠滅おそれや逃亡するおそれがないこと,例えば,被害者との示談交渉を弁護士がすすめていること,両親が身柄引き受けをしていること,勤務先では重要な仕事をしていることなどについての資料を用意して説明し,さらに意見書を提出するなどして説得に努力することが可能です。
本人は身柄拘束をされているため,ご本人に代わって迅速に動けるのは弁護士しかいません。
特に被害者との示談交渉は,ご本人の家族とも会いたくないという被害者も多いので弁護士の役割は重要であるといえます。
不起訴処分・処分保留
逮捕・勾留されても、捜査の結果、犯罪の立証ができないケースもあります。そのような場合、不起訴処分を獲得することができれば、被疑者は留置場から釈放されます。
弁護士は、起訴・不起訴を判断する権限を持つ検察官に面会し、意見書や資料を示し不起訴を求めることができます。
不起訴処分が獲得できると、逮捕された事件について刑事裁判が開かれないことになるので、前科が付くこともありません。そして、法律上何も制限を受けることもなく日常生活を送ることが可能になります。
また,勾留の満期までに検察官が処分を決められない場合は,処分保留で釈放されることもあります。この場合,捜査自体は続きますが,身柄は解放されますので,日常生活に復帰することができます。
略式手続
略式手続とは、検察官が簡易裁判所に対して略式請求を申し立てることにより、公判手続を経ることなく、検察官が提出した証拠のみで100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言い渡す手続です。
この手続きは,公開の法廷に出廷しなければならない公判請求事件と異なり,簡易裁判所の裁判官が,検察官から提出された起訴状と証拠書類,科刑意見を検討して、略式命令を言い渡すというものです。
略式命令がなされると、略式命令を告知した時点で勾留は失効し、身体拘束から解放されることになります。
略式命令で言い渡される罰金又は科料も、刑罰の一つではありますが、裁判確定前でも仮に罰金を支払うこと(仮納付)によって、罰金刑の執行(支払いを怠った場合に労役場留置)を受けずに済み,自宅に戻り、社会生活を送ることができます。
事件の早期解決、身体拘束からの解放という点で、被疑者にもメリットがあるので、事実関係に争いのない事件で、法定刑に罰金又は科料が定められている場合には、略式命令の申立てをするよう、弁護人の方から検察官と交渉することもあります。
その他
勾留決定に対する準抗告(勾留決定に対する不服申立手続き)や勾留取消請求(勾留後の事情の変化により勾留の必要がないと判断される事情がある場合),さらに勾留執行停止申立(ご本人の重篤な病気による診断・治療や入院,そして同居していた親族が危篤状態にある際の面会,親族の葬儀への参加といった理由で認められることがあります。しかし,実弟の結婚式に参加するためであったとしても,これまでの関係から請求が認められなかった事例もあります。)も考えられます。詳細については,ご相談ください。
起訴後の身柄の解放
起訴後の勾留から解放されるために、保釈を目指します。
保釈
事件が起訴された後も,自動的に勾留は続きますが、起訴前と違い起訴後の勾留については、その勾留期間について、「公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。」(刑事訴訟法60条2項)と定められており、長期化する傾向があります。ですので、弁護士を通じて保釈を請求し、留置場又は拘置所からの釈放を目指す必要があります。釈放された後は、自由に職場や学校に通うことができ、旅行や住居に関する一定の制限以外は、今までどおりの日常生活を送ることができます。これにより、自宅から法律事務所に通って、弁護士と打ち合わせを重ね、来る刑事裁判に向けて充実した準備を行うことが可能になります。
なお、起訴後、被告人は拘置所に移送され、そこで身柄拘束が続くことが多いのですが、拘置所では、弁護人であっても、原則として平日しか接見できず、受付時間も厳格に定められています。ですので、拘置所で身柄を拘束されると、警察の留置場にいるときは可能だった平日の夜や休日の接見を行うことは難しいのが現状です。(もっとも、拘置所であっても、刑事裁判の日が近づくと休日や夜間の接見が認められる場合もあります。)刑事裁判に向けて充実した準備を行うためにも、保釈を請求し、認めてもらうことが重要です。
解決事例
ご依頼者様は、強制性交等罪を被疑事実として逮捕されましたが、捜査の結果、強制わいせつ罪で起訴されました。保釈において、権利保釈であれば「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、裁量保釈であれば「罪証を隠滅するおそれの程度」(以下、これらを「罪証隠滅のおそれ」といいます。)と、いずれの場合であっても、被告人が、自らの刑事責任に影響を及ぼしうる証拠に対し、不当な働きかけを行うおそれがあるかどうか、ある場合にそのおそれが高いかどうかが判断要素の1つになっています。そして、実務上、罪証隠滅のおそれは、保釈の判断において非常に重視されています。
ご依頼者様の場合、当該事件の刑事裁判において最重要証拠ともいえる被害者と面識がありました。このような場合、裁判官に、「保釈を認めた場合、被告人は被害者に会いに行って、裁判で被告人に有利な発言をしてくれるよう頼むのではないか。」等と思われる可能性が高くなり、罪証隠滅のおそれが高いとして保釈が認められづらくなります。そこで弁護人は、ご依頼者様が被疑者の段階から、ご家族に連絡を取り、ご依頼者様が保釈を認められた場合に、被害者に会いに行けない環境を整備する活動を行いました。
まず、ご依頼者様が保釈された場合に居住する予定の住居に、監視カメラを設置してもらいました。そして、その監視カメラの映像を、ご家族それぞれのスマートフォンでいつでも見られる状態に設定してもらいました。諸々の事情を総合すると、ご依頼者様は、3時間以上あれば被害者と接触し、住居に戻ることが出来ると考えられたため、ご家族が不在で、ご依頼者様が住居に一人になってしまう場合には、最低でも3時間に1回は映像を確認する必要がありました。そこで、時間と担当を決めて、ご家族で定期的に映像を確認してもらうことにしました。また、万が一カメラが故障した場合に備えて固定電話も設置してもらい、決まった時間になったら、ご依頼者様が住居の固定電話からご家族に電話をかけるという方法で、在宅確認ができる状況を整えました。
このようにご依頼者様の家族と密に連携を取り、罪証隠滅のおそれがないといえる環境を整備し、ご依頼者様が起訴された当日、速やかに保釈請求を行いました。その結果、起訴の翌日には保釈が認められ、晴れてご依頼者様はご家族の待つ住居へ帰ることができました。