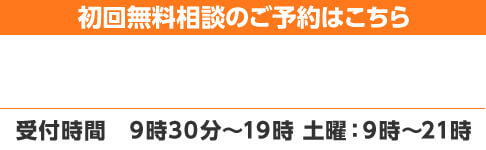目次
勾留延長の阻止
1 勾留延長とは

その後、検察官は、裁判官に対して、身柄拘束期間をさらに10日間延長するように求めることができます(勾留延長請求)。これを裁判官が許可すれば、被疑者とされた人は、合計20日間勾留されることになります(勾留延長。刑事訴訟法208条2項)。検察官は、延長された20日目の勾留の日までに、被疑者とされた人をそのまま起訴するか、釈放することになります。
そして、実際には、検察官が勾留延長請求をして、これに被疑者側から何も反論がなければ、ほとんどの場合、裁判官はそのまま10日間の勾留延長を許可してしまいます。刑事訴訟法の条文には、一応「やむを得ない事由があると認めるとき」に限って延長することができると書かれてはいますが、現状では原則と例外が逆転していると言えます。
2 勾留延長を阻止するためには
しかし、検察官による勾留延長請求に対して、被疑者側が何もできないわけではありません。弁護人が付いていれば、次のようなことができます。
まず、①弁護人が検察官に対し、勾留延長請求をしないよう働きかけることができます。事案によっては、このような弁護人の働きかけに検察官が理解を示し、身柄拘束を延長せずに勾留10日目で釈放することもあります。
他方、②検察官が勾留延長請求をした場合でも、弁護人は、今度は裁判官に対して、検察官の勾留延長請求を却下するように働きかけることができます。その結果、裁判官が弁護人の主張を認めて勾留延長請求を却下すれば、勾留10日目に釈放されます。
さらに、最初の10日間の勾留とは異なり、勾留延長は、(極めて特殊な事案を除き)最大で10日間と決まっているだけであり、一律に10日間ではありません。そこで、③仮に、裁判官が勾留延長を許可したとしても、弁護人の働きかけ次第では、延長の日数が少なくなることもあります。例えば、勾留の延長は許可するが、その延長日数は7日間までしか認めない、といった具合です。
なお、勾留延長の手続には、最初の勾留の手続と比べると、決定的な違いが一つあります。それは、裁判官が、勾留延長請求を許可するか却下するかを決定するにあたり、勾留質問のように直接被疑者から話を聞く手続がないことです。つまり、勾留された本人にとっては、身柄拘束の最終的な決定権者である裁判官に対して、自分の意見を述べる機会が保障されていないのです。こうした事情から、勾留延長を阻止するためには、本人の意見を代弁する弁護人の存在が必要不可欠となるのです。
3 勾留延長を阻止するための具体的な弁護活動
過去の最高裁判所の判例によれば、勾留延長が許されるための要件である「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、「事件の複雑困難(中略)、あるいは証拠収集の遅延若しくは困難(中略)等により、勾留期間を延長してさらに取調べをするのでなければ、起訴もしくは不起訴の決定をすることが困難な場合をいう」とされています(最高裁判所昭和37年7月3日判決・最高裁判所民事判例集16巻7号1408頁)。
弁護人は、この判断基準を念頭に置きながら、検察官や裁判官への働きかけを行います。
例えば、あらかじめ、取調べを受けた時の記録をご本人につけていただき、それをもとに、捜査機関がどのような証拠を収集し終えているのかを推測します。その上で、「警察署や検察官は、すでにこれだけの証拠を収集したのだから、もはや起訴・不起訴の判断に必要な資料は揃っており、これ以上身柄拘束をしてまで取調べをする必要はないはずだ。」と主張します。
その他、勾留延長以前の問題として、そもそも刑事訴訟法上の勾留の要件を満たしておらず、身柄拘束自体が違法と考えられる事案であれば、改めて、そのことを主張します。
4 勾留延長を阻止する弁護活動の意義
捜査段階における弁護活動の獲得目標には様々なものがありますが、これまで、勾留請求却下や不起訴などと比べると、勾留延長請求却下は、あまり注目度が高くなかったように思われます。それは、現在の運用実務において、いったん勾留が認められると勾留延長請求却下を獲得することがかなり難しくなってしまうということも、影響しているのかもしれません。
しかし、事案によっては、勾留延長を阻止する弁護活動にはとても大きな意義があるのです。
ここで、ある会社員の方が、いきなり逮捕されてしまったと仮定します。逮捕と最初の勾留の期間は、法律上最大で13日間ですが、実際の運用では12日間になることが多いです。そのため、逮捕された日が月曜日でない限り、逮捕・勾留期間中に2回、土日が到来することになります(逮捕された日が月曜日でも、土日は1回到来します)。これが何を意味するかということですが、この方の勤め先が、土日を定休日とする一般的な会社の場合、12日間勾留されるとは言っても、実際に職場を休むのは10日間以下になるということです。
そして、様々な方の刑事弁護を担当してきた経験からすると、実は、「休むのが10日間以内であれば、有給休暇をとるなどして、なんとか職場には逮捕されたことを話さずに済む。」という方が、少なくないのです。
ところが、勾留延長が決まって、さらに身柄拘束期間が長引けば、会社に対しては、事情の説明がなかなか難しくなってきます。その結果、逮捕されたことを正直に話さざるを得ない状況となることがあります。そうはならなくても、突然の長期の欠勤が会社内で問題視され、その後の昇進・昇給に響くということもあり得ます。
実際、当事務所で過去に担当したある事案において、被疑者とされた会社員の方は、最初の10日間の勾留による欠勤だけなら会社にも説明がつくものの、さらに10日間の延長となれば会社に説明がつかず、正直に逮捕のことを話さなければならない、という状況に置かれていました。そこで、ご本人やご家族と協力し、勾留延長を阻止するための活動を展開したところ、裁判官が検察官の勾留延長請求を却下し、ご本人はその日のうちに釈放されました。その結果、ご本人は無事職場に復帰し、それまでと変わらない生活を取り戻すことができました。
このように、勾留延長されるか否かが、事案によっては、それまでどおりの社会生活を継続できる否かの分かれ道になっていることがあるのです。その意味で、勾留延長請求却下などにより勾留延長を阻止する弁護活動には、大きな意義があると言えます。