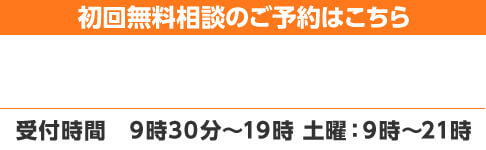目次
背任罪
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与える犯罪です(刑法第247条)。
背任罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
特別背任罪
会社法第960条1項には、特別背任罪が定められています。
取締役など会社で重要な役割を担う人物が、背任行為を行った場合に、背任罪よりも重く処罰されるというものです。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と定められています。
背任罪の要件
背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者」です。「他人」とは事務処理の委託者で、本条の「本人」と同じです。「他人のためにその事務を処理する者」には、自然人のほか、国、地方公共団体、法人、法人格なき社団なども含まれます。
①他人から委託された事務
背任罪は財産犯であるため、委託された事務は財産上の事務に限られるというのが通説とされています。また、「他人のために」事務を処理することが必要なので、自己の事務にとどまるものは単なる債務不履行にすぎないと言われています。
②任務に背く行為(任務違背行為)
「任務に背く行為」とは、本人からの信任委託の趣旨に反する行為を意味します。信任委託の趣旨の沿った行為である限りは、本人に損害が発生したとしても、背任罪は成立しません。どんな場合に信任委託の趣旨に反するかは、事務の内容、事務処理者の権限、当時の状況などに照らし、期待されていた行為をしたか否かで判断されます。
裁判例:信用保証協会の職員がまともな信用調査をせずに担保力の弱い中小企業の債務保証をした場合(最高裁判所昭和58年5月24日決定)
③図利加害目的
「自己若しくは第三者の利益を図る目的」(図利(「とり」と読みます。)目的)又は「本人に損害を加える目的」(加害目的)の、少なくともいずれかを必要とします。ここにいう「第三者」とは、自己又は本人以外の者を指します。
背任罪が成立するためには、図利加害目的が必要なので、委託をした本人の利益を図る目的で行為に出た場合は、背任罪が成立しません。なお、自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的が混在する場合は、目的の主従により背任罪が成立するか否かが決められます。本人の利益を図る目的が決定的な動機でない場合には、背任罪の図利加害目的が認められることになります。(最高裁判所平成10年11月25日決定)
④財産上の損害
「財産上の損害」とは、判例上は、「経済的見地において本人の財産状況を評価し、被告人の行為によって、本人の財産的価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」(最高裁判所昭和58年5月24日決定)とされています。
これから、以下のことが分かります。
・経済的見地から判断するので弁済可能性が乏しい者に貸し付けたときは、同額の債権が存在したとしても、損害を観念できます。
・本人の財産状況を評価するということは、片方で損害があったとしても、もう片方でこれに対応する利益があれば、全体として損害とはいえないということです。
・財産上の損害は既にある財産が減少する積極的損害だけでなく、増加すべき財産が増加しなかった消極的損害も含みます。
背任罪で逮捕されたら
逮捕された場合、身体拘束が予想される期間は下記の通りです。
⇒逮捕されると48時間
⇒勾留決定がなされると10日間(勾留延長があれば、さらに10日間)
⇒起訴された場合は保釈が許可されるまで身体拘束が継続
もちろん事件の内容によっては、数日で釈放となる場合もあり得ますが、最長の場合には捜査段階で最大23日間程度の身体拘束が予想されます。勾留が決定してしまうと、長期に渡る身体拘束を受けることとなり、職場等への影響は避けられません。
逮捕から勾留請求まで
逮捕された警察署で取り調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。検察官の取り調べで、さらなる身柄拘束の必要があると判断した場合は、裁判官に被疑者を勾留するように請求します。
また、逮捕から勾留が確定するまでの間(最大で72時間)は、弁護士以外の面会は認められない場合がほとんどです。
勾留
勾留とは逮捕に引き続き身柄を拘束する処分のことを言います。
勾留するには、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があること」に加え、以下の3点のうち、ひとつ以上該当することが必要となります。
・決まった住所がないこと
・証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること
・被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること
検察官の勾留請求が裁判所に認められた勾留決定が出された場合には、最大で10日間の身体拘束を受けることになります。さらに、捜査が必要と検察官が判断した場合にはさらに10日間勾留が延長されることがあり、最大で20日間勾留される可能性があります。
検察官による最終処分
検察官はこの勾留期間に取り調べの内容や証拠を審査し、起訴か不起訴かを判断します略式請求の場合を含め、一旦、起訴されれば、ほぼ確実に刑事罰を受けることになります。
不起訴となれば前科がつくことはありません。もし、被疑者が犯行を認めていたしても、犯行を立証するに足る証拠がない、情状(被疑者の性格・年齢・境遇・行為の動機や目的など)を鑑みて処罰の必要がないなどの理由から検察官が不起訴の判断する場合があります。
弁護士ができること
事実関係の調査
背任罪は、要件が厳しく、比較的起訴率が低い犯罪なので、徹底的に事実を調査し、すべての要件を満たすか否か(特に、図利加害目的・財産上の損害)を確認する必要があります。
会社との示談交渉
そして背任罪が成立すると判断した場合は、他の財産犯と同じく、被害企業と示談、弁償を尽くし、告訴や被害届が提出されないよう働きかけることに努めます。また、例え告訴や被害届が提出された場合であっても、多くの被害者は、被害回復を第一に考えている場合が多いことから、被害者と徹して示談協議を行い、告訴や被害届の取り下げをしてもらうことで、事件の立件化を防ぐ、もしくは不起訴処分を得るよう努めます。