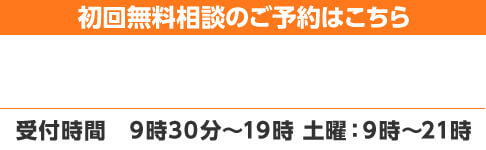目次
1 時効とは何ですか?
刑事事件に関するニュースなどで、時効が成立したなどと言う言葉が使われることがあります。弁護士などの法律のプロであれば時効についてよく知っているでしょうが弁護士でもない一般人には分かりにくいものです。
時効とは、法律上の用語で、犯罪が発生して一定期間が経つと、裁判でその犯罪の罪を認定してもらうための起訴ができなることをいいます。刑事事件では、検察官が犯人を起訴して刑事裁判にかけますが、犯罪行為が終わってから一定の期間が過ぎると、その犯人を起訴できなくなるということが刑事訴訟法に規定されています。これを公訴時効と言います。
ニュースでは「時効成立の数時間前に犯人が逮捕された」などと大々的に取り上げられることがありますが、通常は逮捕から検察官の起訴・不起訴の判断までに一定期間を要するため、かなり稀なケースであると言えます。
ひとたび時効が成立すると、警察はその犯人を逮捕できなくなってしまって、時効が成立した事件については、警察が事件を被疑者不詳として検察官に書類送検し、かつ、検察官が事件を「時効完成」として不起訴処分に付し、これにより事件は完結してしまいます。犯罪の種類によって時効期間はさまざまです。
2 時効制度の理由は何ですか。
刑事事件などで時効というものがたびたび注目される、一定期間経過したら犯罪を処罰することが出来なくなる時効制度ですが、なぜ時効制度が存在するのかが不思議に思う人も多いはずです。当然、いつ証拠が見つかるか分からないので、いつまでも捜査対象とすべきという考え方にも一理あります。
刑事事件に時効制度が存在する理由としては、時間とともに証拠がどんどんと消えていって、犯罪の証拠集めができにくくなるということがあります。時間が経てば経つほど、人の記憶もあいまいになっていきますし、残された証拠も散逸してしまいます。犯罪を立証するために必要な証拠を集められる期間には、限界があるといえます。また、不十分な証拠で捜査を行うと冤罪を引き起こす可能性もあります。
また、事件に割ける捜査官の人員と労力にも限界があり、全ての事件をずっと捜査し続けることも限界があるといえます。事件の重大さで時効の期間に長短があるのもこのためといえます。
なお、時間の経過により、処罰感情や社会的影響が薄れるため処罰の必要性が減るという考え方もあります。ですが、近年殺人事件など重大な犯罪に関しては時効が廃止されたように、時効に関する考え方は時代とともに変化しつつあるといえます。
3 時効の進行が停止するのはどのような時ですか。
時効は犯行が終わった瞬間から進行していきますが、時効が一時的に停止する場合については、刑事訴訟法に定めがあります。
以下のような場合に一定期間時効が停止するとされています。
・起訴された場合
時効は、起訴が行われると停止し、その裁判が確定すると再び進行を始めます。裁判が長期化しても、その途中で時効になることはないといえます。
共犯者がいる場合は、共犯者の時効も停止します。
・犯人が海外にいる場合
犯人が国外にいる場合には、国外への捜査は基本的に外国政府に捜査協力を求める形しかできないため時効が停止します。これは犯人が捜査から逃れることを防止する意味合いがあります。
・犯人が逃げ隠れしているため起訴状が送れなかった場合
起訴された犯人が逃げ隠れしていることで、有効に起訴状の謄本の送達ができなかった場合、公訴棄却の裁判が下されますが、起訴から公訴棄却裁判までの間は、時効は進行を停止します。公職選挙法違反事件などにおいては、このような事例の場合、時効完成を阻止するため、控訴棄却後に敢えて起訴を繰り返すケースもあるところです。
4 時効の廃止
時代が進むにつれ、DNA鑑定など昔ではできなかった捜査ができるようになってきて、時効制度の理由が薄らぐ部分も出てきました。そこで、2010年法改正が行われ、殺人罪、強盗殺人罪など法定刑の上限が死刑であるものについては、改正前は公訴時効期間が25年であったところ、改正後は公訴時効が廃止されました。
また、その他の罪についても、公訴時効が延長されたものがあります。すなわち、法定刑の上限が無期の懲役・禁錮であるものについては、公訴時効期間が15年から30年に、法定刑の上限が20年の懲役・禁錮であるものについては、公訴時効期間が10年から20年に、法定刑の上限が懲役・禁錮で、①及び②以外のものについては、公訴時効期間が5又は3年から10年に変更されました。
5 その他の罪の公訴時効
その他の代表的な犯罪の公訴時効は、以下の通りです。
|
罪名 |
公訴時効 |
|
窃盗罪(235条) |
7年 |
|
強盗罪(236条) |
10年 |
|
傷害罪(204条) |
10年 |
|
暴行罪(208条) |
3年 |
|
脅迫罪(222条) |
3年 |
|
名誉毀損罪(230条) |
3年 |
|
侮辱罪(231条) |
1年 |
|
恐喝罪(249条) |
7年 |
|
詐欺罪(246条) |
7年 |
|
横領罪(252条) |
5年 |
|
業務上横領罪(253条) |
7年 |
|
背任罪(247条) |
5年 |
6 民事の時効
時効には刑事の公訴時効の他に、民事にも消滅時効があります。民事の時効が経過すると、加害者が時効を援用した場合(「援用」とは、自分に有利に時効制度を利用する場合を言います。)は、被害者に損害賠償を支払う義務が消滅することになります。そのため、損害賠償を請求されたとしても、消滅時効が成立しているため請求権がないと主張することができます。
民事の時効は「損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については5年)、不法行為の時から20年」とされています。
7 懲戒処分
民事や刑事と違い懲戒処分には時効が設けられていないため、行為から長時間経過しているとしても懲戒処分を請求される可能性があります。
ただ、弁護士や司法書士などの資格職に対する懲戒請求には時効期間が設けられているケースもあります。
8 親告罪の告訴期間
公訴時効と似た制度として「告訴期間」が存在します。
告訴期間とは、犯罪の被害者などが刑事告訴できるまでのタイムリミットを指します。告訴期間が経過してしまうと、たとえ公訴時効が成立していない段階でも告訴ができなくなるため、犯人は罪を問われません。
刑事訴訟法第235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない」と明記しています。
親告罪とは起訴をするために被害者の告訴が必要な犯罪を指します。
親告罪には、名誉棄損罪、過失傷害罪、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪などがあります。
9 時効に関する相談事例等
被害者が加害者に対し、刑事告訴を行おうとする場合や民事の不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起しようとする場合、まず時効が成立していないかを検討しておくことが必要となります。
公訴時効や民事の時効が成立してしまった後では、告訴や訴え提起ができなくなりますし、刑事告訴の場合、時効成立までの期間が短い場合は、それだけで告訴を受け付けてもらえないことがしばしば起こりますので、早めの対応が肝要です(通常、告訴事件では、少なくとも、捜査の時間として半年が必要です)。
ただし、民事事件では、時効が成立しているかに見えても、加害者が被害者に対し権利の承認をしている場合(賠償義務を認める謝罪文などを被害者に交付した場合など)は時効更新となり、時効が完成していないと認められることもあります。このほかにも、時効については、仮処分・仮差押、催告による完成猶予などがあります。弁護士にご相談ください。
また、刑事、民事を問わず、時効がいつから始まったと見るか(時効の起算点の問題)は、事案によって検討すべきです。例えば、横領行為を繰り返していた事案については、全体の流れの中で、いくつかの行為につき時効が来ていたとしても、最終行為が時効完成でなければ、一連一体の行為とみて、全体につき、告訴、損害賠償請求が可能と判断
されることもあります。難しい問題点ですので、弁護士によくご相談ください。
また、詐欺、横領等のやや複雑な財産犯では、場合によって、警察相談段階で資料を整理して、時効が成立していない部分を分かりやすく説明する必要も出てきます。
当事務所では、様々な警察署で告訴等の相談をした経験があり、時効に関してもノウハウの蓄積があります。お悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。