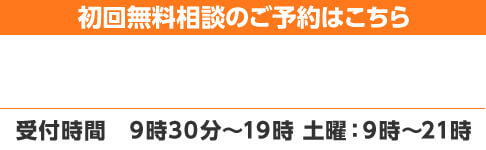目次
放火罪
建造物等へ故意に火を放った場合、放火罪に問われます。
放火した建物に人がいたか、どのような建造物であったかなどによって、問われる罪名が変わってきます。
以下、解説します。
現住建造物等放火罪(刑法108条)
現住建造物に故意に放火をした場合、現住建造物等放火罪に問われます。
現住建造物とは、「現に人が居住として使用している、もしくは人がいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)」を指します。
法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」で、放火罪の中で最も重い類型です。
未遂の場合
刑法第112条は、現住建造物等放火罪について、未遂であった場合でも罰すると規定しています。そのため、未遂の場合でも既遂の場合と同じ刑が適用されることになります。未遂の場合は刑が減軽されることもありますが、必ずというわけではなく裁判所の判断に依ります。
現住建造物等放火罪で未遂となるのは、目的物に放火をしたものの、焼損させるに至らなかった場合などです。また、「焼損」の意義について、よく、火が媒介物を離れて目的物に移り、独立して燃焼作用を継続し得る状態に達した時点を指すなどと言われています。もっとも、近時、難燃性建造物は独立燃焼に至らないものの、有毒ガスの発生等によって、当該建造物の住民等の生命・身体への危険が生じ得ますので、焼損させるに至ったといえるか言えないかは、ケースバイケースともいえます。
非現住建造物等放火罪(刑法109条)
非現住建造物に故意に放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われます。
非現住建造物とは、「現に人が住居として使用せず、かつ、現に人がいない建造物(空き家・倉庫など)、艦船又は鉱坑」を指します。
法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
自らが所有する建造物を放火したという場合には、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」となります。もっとも、自己の所有物であっても、他人に賃貸していたり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされます。
また、自己の所有する非現住建造物への放火は、「公共の危険」を生じさせた場合にのみ処罰されることになります。
建造物等以外放火罪(刑法110条)
上記以外の物に故意に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪に問われます。具体的には、自動車やバイクなどに放火したケースです。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
前述のようにその対象物が放火した物が自己の所有物であれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と規定されています。本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害がある場合は他人の所有物とみなされます。
失火罪(刑法116条)
過失によって出火させ物を焼損させてしまった場合は、失火罪に問われます。
放火罪が故意によるものであるのに対し、失火罪は過失によるものとなるため、失火罪の方が罪は軽くなります。
刑罰は「50万円以下の罰金」です。
失火により焼損した物が、現住建造物、他人の非現住建造物、または自己の非現住建造物、建造物等以外の物(刑法110条)で公共の危険を発生させた場合に本罪の対象となります。
業務上失火罪(刑法第117条の2)
業務上必要な注意を怠り、失火により物を焼損させてしまった場合は、業務上失火罪に問われます。
調理師や溶接作業員、ボイラー技士など火気取り扱う仕事に就いている人だけでなく、火災の発見や防止する職務のある警備員などにも本罪が適用される可能性があります。
刑罰は、「3年以下の禁錮または150万円以下の罰金」で、失火罪よりも重くなります。
重過失失火罪(刑法第117条の2)
重大な過失により出火させ物を焼損させてしまった場合は重過失失火罪に問われます。
重過失とは、わずかな注意を払っていれば容易に火災の発生を防止できた状態を指します。
刑罰は、「3年以下の禁錮または150万円以下の罰金」で、失火罪よりも重くなります。
逮捕の可能性
逮捕された場合、身体拘束が予想される期間は下記の通りです。
⇒逮捕されると48時間
⇒勾留決定がなされると10日間(勾留延長があれば、さらに10日間)
⇒起訴された場合は保釈が許可されるまで身体拘束が継続
もちろん事件の内容によっては、極めて例外的な場合、数日で釈放となる場合もあり得ますが、最長の場合には捜査段階で最大23日間程度の身体拘束が予想されます。勾留が決定してしまうと、長期に渡る身体拘束を受けることとなり、職場等への影響は避けられません。
逮捕から勾留請求まで
逮捕された警察署で取り調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。検察官の取り調べで、さらなる身柄拘束の必要があると判断した場合は、裁判官に被疑者を勾留するように請求します。
また、逮捕から勾留が確定するまでの間(最大で72時間)は、弁護士以外の面会は認められない場合がほとんどです。
勾留
勾留とは逮捕に引き続き身柄を拘束する処分のことを言います。
勾留するには、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があること」に加え、以下の3点のうち、ひとつ以上該当することが必要となります。
・決まった住所がないこと
・証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること
・被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること
検察官の勾留請求が裁判所に認められた勾留決定が出された場合には、最大で10日間の身体拘束を受けることになります。さらに、捜査が必要と検察官が判断した場合にはさらに10日間勾留が延長されることがあり、最大で20日間勾留される可能性があります。
検察官による最終処分
検察官はこの勾留期間に取り調べの内容や証拠を審査し、起訴か不起訴かを判断します。
故意犯である放火罪の場合は、特段の事情がない限り、起訴の可能性が高いといえます。
一旦、起訴されれば、無罪判決とならない限り、ほぼ確実に刑事罰を受けることになります。
不起訴となれば前科がつくことはありません。
もし、被疑者が犯行を認めていたしても、犯行を立証するに足る証拠がない、情状(被疑者の性格・年齢・境遇・行為の動機や目的など)を鑑みて処罰の必要がないなどの理由から検察官が不起訴の判断する場合があります。
弁護士ができること
被害者との示談交渉
放火罪の事件で少しでも軽い処分・刑罰を得るためには、被害者と示談をすることが重要です。被疑者・被告人が身体拘束されている場合、ご本人が示談交渉に動くことは物理的に不可能ですから、弁護士が代理人として示談交渉に動かざるを得ません。この場合の弁護士の必要性は明らかです。
他方、被疑者・被告人が身体拘束されていない場合や身体拘束から途中で解放された場合であっても、加害者と直接のかかわりを持つことを嫌悪する被害者の方が多いため、弁護士が示談交渉に臨むことには大きな意義があります。
そこで、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者との示談が成立すれば、比較的軽い類型の放火罪や犯情の軽い放火罪であれば、不起訴処分となり得ます。また、現住建造物等放火罪のように重い類型の放火罪であっても、起訴された後の判決の段階で示談が有利に考慮されることは十分にあります。
解決事例
当事務所は、現住建造物等放火罪、建造物以外放火罪に問われた事件について、加害者側のご依頼を受け、刑事弁護を行った実績を複数有しております。
このうち建造物以外放火(自動車放火)の事例では、当事務所の弁護士が被害者(自動車の所有者)との間で粘り強く示談交渉を行った結果、示談が成立し、加害者を許す旨の文言を得、不起訴処分となりました。
早期に弁護依頼を頂くことによって、当事務所の弁護士は、事案に応じた迅速かつ適切な対応を取ることができます。本罪関連の事件につきましては、ぜひ当事務所に早期にご相談ください。